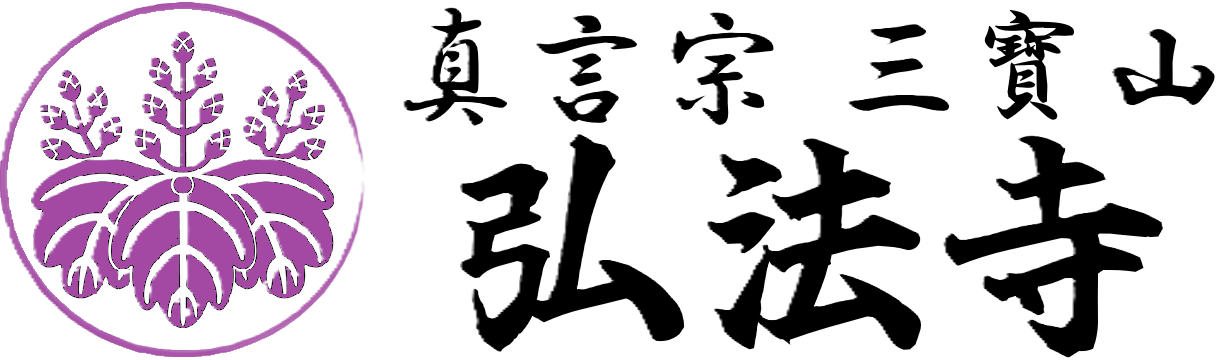弘法寺は、高知県高知市の北秦泉寺という地域にあるお寺でございます。
火渡りの寺、柴燈護摩の寺とも呼んでいただくことがございます。
寺院名:三寳山 地蔵院 弘法寺
宗 派:真言宗 醍醐派
御本尊:子安延命地蔵大菩薩 大日大聖不動明王 毘沙門天
寺院名:三寳山 地蔵院 弘法寺
宗 派:真言宗 醍醐派
御本尊:子安延命地蔵大菩薩
大日大聖不動明王 毘沙門天
当初、常慶寺は千三百年前に秦泉寺の末寺として建立されたと云われています。
当寺は、住職の霊験によると御本尊様は薬師如来様と毘沙門天様であったと思われる。
江戸の初期に土佐城主、山内家の入国の際、家臣であります前川家持仏延命地蔵菩薩を納め、仙石家持仏千手観世音菩薩と
阿弥陀如来様を納め前川家と仙石家の菩提寺として帰依し奉り明治の初めまで栄えて来たと云われています。
明治の始めに神佛分離令、廃仏毀釈の法難に依り、寺は壊され、焼かれ、本尊様は小さい御堂で祭っておりました。
明治十年に眞言地蔵宗の修験道を創設し活動、明治三十九年三月二十八日不動尊の御縁日に修験道結社修験根本道場として
復興し、先代住職志摩征覚師、地区民一同で守り祭られてきました。
昭和二十七年に宗教法人法が改正された時、先代住職征覚師によって弘法寺、現在の香美市土佐山田町新改、弘法谷より
当地(北秦泉寺)に移転し現在に至るのでございます。
弘法寺は大師様、十九歳の砌、地区民の厄払い諸々の祈願の為、行をし、不動明王を刻み祀ったと云われており、後に大師様が
有名に成りますと宗祖弘法大師様が行をし、祈願をしたところでありますので地名も弘法谷と成り弘法寺ができたと云われています。
弘法寺も千二百年の歴史が有り現在に至っております。
其の後、先代住職が遷化し三十年程無住で有りましたが、現住職祥元が縁有って弘法大師様の導き、地域の方々の思い、話し合いに依り、昭和六十二年二月より土地を購入し、全てを受け継ぎ、昭和六十三年に地域の信者様、多くの方々の賛同を得て、本堂を建立しました。
又、平成五年には護摩堂を建立、平成九年には庫里を建立しました。平成十年には裏山を購入し、平成十年より多くの方々の寄進に依って新四国八十八ヶ所を建立し開設。
今では毎年四月の初め各御寺院様乃御助法を得てお砂踏法、毎年十二月第一日曜日は各御寺院様、神職様、修験者、御詠歌講員の方々の御助法を得て柴燈護摩火渡り行を厳修しております。